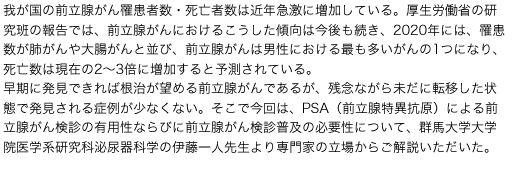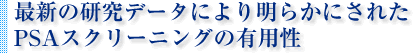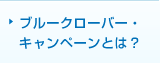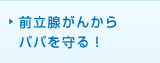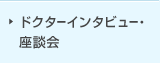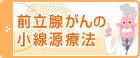|
|---|
前立腺がんは人種、遺伝、様々な環境因子によって罹患率が大きく異なりますが、各国の検診普及率、がん登録の精度の違いなどにより、正確な国際比較は困難といわれています。かつて我が国の前立腺がん罹患率については、欧米の1/5〜1/10程度の低いものと考えられていましたが、近年、PSA検査の導入や生検方法の診断技術の向上などにより、我が国の前立腺がんの正確な実状が明らかになり、以前考えられていたような日欧米間格差はないことがわかってきました。現在、罹患率、死亡率ともに右肩上がりに増加しており、今後も、高齢化や生活様式の欧米化の要因などもさらに影響し、増加し続けると予測されています(図1)。
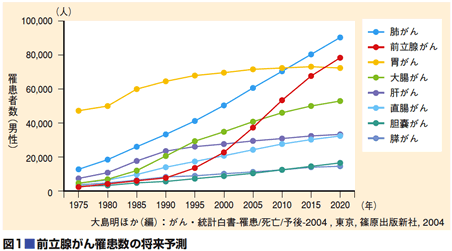
一方、前立腺がんが社会問題になっているアメリカでは、PSA検診の普及に伴い、1992年のピーク以降、前立腺がん死亡率は減少に転じています。2008年の前立腺がん死亡者数のデータでは、日本が9,985人であるのに対しアメリカが約27,000人でした。両国の男性人口に2倍以上の差があることを考えると、日本の死亡率がアメリカにかなり近いレベルにまで上昇していることがわかります。
前立腺がんは、限局がんや局所進行がんといった転移のない時期に見つかれば、治療効果も高く根治が望めますが、転移がんでは根治が極めて難しく、治療法の選択肢も限られ、初期治療としてホルモン療法の効果は望めますが、半数の方は5年以内に死亡してしまいます。つまり、前立腺がんにおいては転移が起きる前にがんを発見し、そして適切な治療につなげることが極めて重要です。
前立腺がん検診の重要性を示すデータとして、住民検診で発見された前立腺がんと、主に何らかの排尿に関連する症状を伴って泌尿器科外来を受診し発見された前立腺がんの臨床病期を比較した群馬県の調査研究があります(図2)。
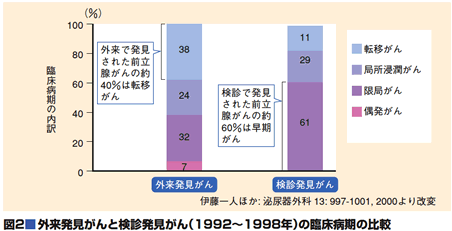
これを見ると、外来発見がんでは転移がんの割合が多く、検診発見がんでは約90%が転移を伴わない段階で発見されていることがわかります。また、臨床病期の分布には住民のPSA検診暴露率が大きく影響をしており、検診を実施していない自治体や検診の受診率が5%以下の自治体で発見される前立腺がんは約30%が転移がんであることがわかっています。日本の検診暴露率は10%程度と予測され、国全体が未だに低い状況にあるため、治療を要する多くの前立腺がんを進行するまで見逃しています。
一方、1992年以降、転移がんが激減し前立腺がん死亡率が低下し続けているアメリカでは、50歳以上男性のPSA検診暴露率が75%に達しています。今のところ前立腺がん死亡の危険を回避できるような効果的な1次予防がないことから、2次予防としての前立腺がん検診の普及とその後の適切な治療が、死亡率上昇に歯止めをかけるためには必要です。
今までも、PSA検診の有用性については、いくつかの信頼性の高い研究がありました。オーストリアのチロル地方で行われた時系列研究は、死亡率減少効果に関する研究として信頼性が高いものの1つです。チロル地方では、1988年から直腸診とPSA測定による前立腺がん検診が導入され、1993年からは45〜75歳の住民に対し無料でPSAスクリーニングが提供されるようになりました。その後、2005年には、検診暴露率は対象住民の87%に達しています。チロル地方では、PSAスクリーニングの普及に伴い、発見される前立腺がんの臨床病期に劇的な変化が起こり、その後速やかに死亡率の大幅な低下が認められました。また、カナダのケベックやイタリアのフィレンツェにおいて実施された検診群と非検診群とを比較したコホート研究では、検診群で前立腺がん死亡率が50〜60%下がることが明らかにされました。
それらの検診の有効性を示した今までの研究結果を確定的なものにしたのは、今年3月のNew England Journal ofMedicine(NEJM)電子版にて発表された、European Randomized Study of Screening for Prostate Cancer(ERSPC)の前立腺がんに対するPSAスクリーニングの有効性に関する研究結果の第一報です。ヨーロッパで進行中の無作為化比較対照試験(RCT)であるERSPCは、今回、中核となる年齢層である55〜69歳での分析を行い、平均8.8年間の観察で、検診群が非検診群に比べて20%の有意な死亡率減少効果を示しました(図3)。エビデンスレベルの最も高いRCTにおいて有意差が得られたことの意義は大きいといえます。
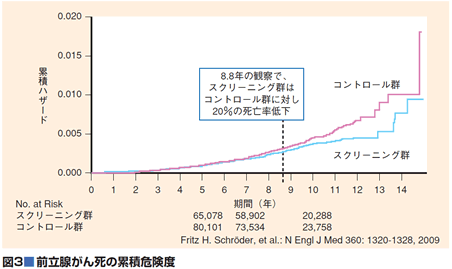
これまでの日本のがん検診は、検診を受診することによりどういったメリットとデメリットがあるのか十分に情報提供することなく、住民への受診勧奨が行われていたことが問題と考えられます。本来、理想的ながん検診は、最新の正しい情報提供に基づき、本人の意志によって任意に受けるものでなくてはなりません。価値観は個々人で異なりますので、がん検診を受けることによるメリットとデメリットに対する捉え方も異なって当然です。今回、死亡率減少効果が明らかになったPSA検診においても、検診を受診することのメリットとデメリットに関する正しい情報を伝え、個々の価値観に照らし合わせて受診するか否かを決定してもらうことが大切と考えられます。「前立腺がん検診ガイドライン:2009年度追補版」(日本泌尿器学会編)では、このことを最重要事項として盛り込み、今後、実際の検診の場に展開をする準備を着々と進めています。
具体的には、前立腺がん検診の最も重要なメリットは、最新の研究結果で明らかにされた死亡率減少効果です。スクリーニング検査であるPSA測定自体にはほとんど不利益はなく、精密検査の前立腺生検においても、重篤な合併症は極めてまれですので、他のがん検診の精密検査と比べて許容範囲と考えられますが、がん診断後の、特に高齢・悪性度の低いがん・小さい限局がんの方で危惧される過剰診断・過剰治療、積極的な治療後のQOL障害が主なPSA検診のデメリットです(表1)。過剰治療のリスクは特に欧米で問題となっており、我が国では少ないといわれていますが、その対策は重要です。今後PSA監視待機療法の適応症例や経過観察方法が確立されることで、過剰治療のリスクが少なくなると考えられます。また、QOL障害についても、低侵襲治療の進歩によって少なくなっていくことは間違いありません。
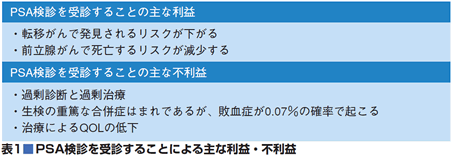
今年4月に開催された米国泌尿器学会(AUA)年次総会において、PSA検査実施年齢をこれまでの50歳から40歳にまで引き下げた新しい「PSA検査に関するガイドライン」が発表されました。AUAが受診年齢を40歳に下げた理由の1つは、将来の前立腺がん発症リスクを正確に把握するうえで、40歳の時点でのPSA基礎値が客観的データとして大変に有用であるからです。もう1つは、将来がんが発見された際、40歳からのPSA値のデ−タがあれば、がんの悪性度の動的な指標として重要といわれているPSA上昇速度を正確に算出でき、それがより適切な治療法の選択に有用な情報となるからです。
今回のAUAの提案したPSA検診開始年齢の引き下げは、先進的ではありますが科学的には妥当といえるため、その提案は日本の検診システムに合った形で反映させるべきと考えられます。我が国のPSA検診システムは、60歳以上の受診者が80%を占める住民検診と、59歳以下の受診者が70%を占める人間ドックでのPSA検診によってバランスが維持されています。住民検診ではがんを発見することを目的としますので、従来通り50歳以上を受診対象とし、個人や企業が費用負担をする人間ドックや職場健診では40歳で受診機会を提供することが、受益者負担の観点と受診年齢層の分布の実状からみて良いと考えます。
またPSA検査の受診間隔に関しては、費用対効果比と検診の効率を考えて設定することが重要です。「前立腺がん検診ガイドライン:2008年度版」(日本泌尿器学会編)では、PSA基礎値が、1.1〜4.0ng/mlの症例においては毎年、0.0〜1.0ng/mlの症例においては3年に1度の受診が推奨されています。今後も増加が予測される日本の前立腺がん死亡率を、アメリカのように減少に転じさせるために、我が国でも住民検診や人間ドックでのPS A検診受診機会を広げ、正しい情報提供に基づいたPSA検診を早急に普及させる必要があると考えます。
![主催:ブルークローバー・キャンペーン運営委員会[(財)日本対がん協会、NPO法人大丸有エリアマネジメント協会、朝日新聞社]
後援:(社)日本泌尿器科学会、日本人間ドック学会、日本放射線腫瘍学会、(財)前立腺研究財団
特別協賛: アストラゼネカ株式会社
協賛: 日本メジフィジックス株式会社、ベックマン・コールター株式会社
協力: 福助株式会社](../images/interview/credit.gif)

![[前立腺がん検診の死亡率減少効果が明らかに] PSA検診の普及と適切治療が命を救う 伊藤 一人 先生(群馬大学大学院医学系研究科 泌尿器科学准教授)](../images/interview/interview_a_title.jpg)