
認知症診療に活かす 脳血流SPECT検査
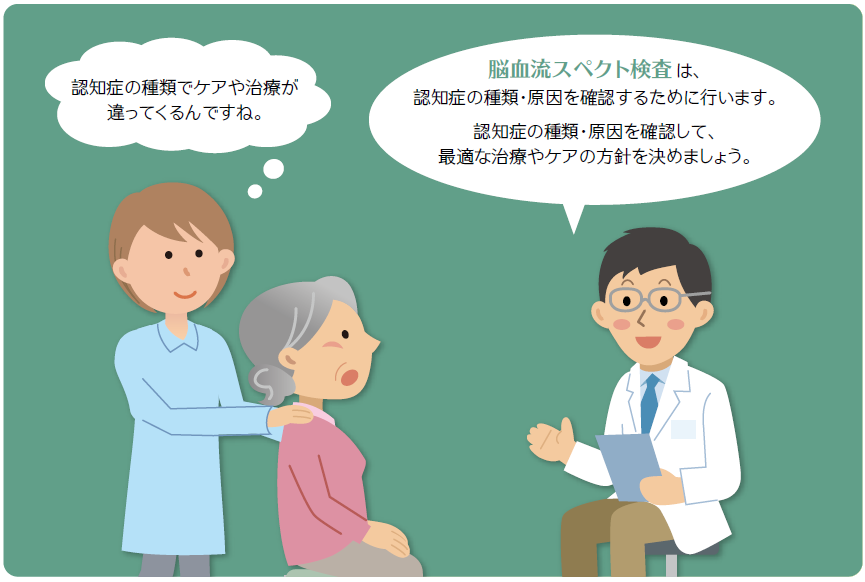
かかりつけ医・認知症サポート医・認知症予防専門医として、画像診断機器をもたない当院が、どのように認知症診療に脳血流SPECTを含む画像診断を活用しているかを紹介します。
1)CNS Spectrums. 2012, 17: 176-206.
2)European Journal of Neurology. 2012, 19: 1487-1511.
3)認知症疾患 診療ガイドライン 2017
まとめ
●クリニックの認知症診療医の立場から、認知症診療における脳血流SPECTの活用方法についてまとめました。画像診断を行うには連携医療機関等に依頼するなど、ハードルは高いように思われますが、連携医療機関から得られる情報は貴重です。
●脳血流SPECTは認知症の早期診断や、鑑別診断のための診断情報が得られます。そのため患者・ご家族・介護者への病気の症状や、これからの治療・介護の方針説明においても、血流低下部位を可視化した画像診断の結果を利用することは有用です。
●我々かかりつけ医やサポート医が認知症診療のゲートキーパーとなるべきであり、日々の研鑽に加えて日常診療で認知症患者の症候と画像診断、特に脳血流SPECT検査の結果を対比させながら総合的に判断していくことは重要です。
●脳血流SPECT検査を実施できる近隣の医療機関と緊密に連携しながら、増加する認知症患者に対応して、客観・公正な判断を行い、治療介護方針を決定することが大切であると考えます。

